不妊治療特集 「保険適用の前に知っておきたい不妊治療の世界」
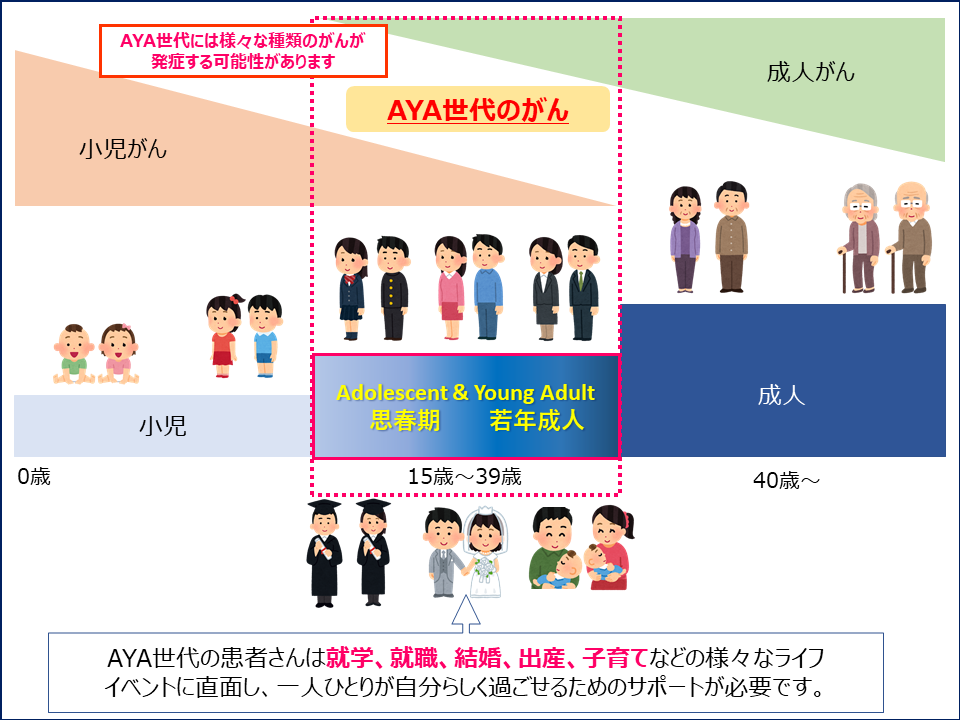
PAST ARTICLES
不妊の世界にスポットが
費用の高い体外受精などの不妊治療に対して菅義偉首相が、公的医療保険の適用を打ち出して以来、これまでメジャーではなかった「不妊の世界」にスポットがあたり始めた。
中高生の間に保険教育をあまり受けてこずに産み時を逃した世代が堂々と悔しさや苦しみの声をあげられるようになり、リアルの経済格差がそのまま映し出される世界に楔(くさび)が打ち込まれた。
中高生の間に保険教育をあまり受けてこずに産み時を逃した世代が堂々と悔しさや苦しみの声をあげられるようになり、リアルの経済格差がそのまま映し出される世界に楔(くさび)が打ち込まれた。
筆者がつい先週会った40代の女性起業家A子さん(子ども2人、ひとりは0歳)も、
「夫婦両者に問題があったため、子どもを授かるのに1000万円近くかかった。うちは早くから、体外・顕微受精でした。保険適用、早くしてほしかったです」
と、堂々と話していた。
しかし、不妊というあまりにも深い世界のほんの一部がつまびらかになったに過ぎないことを筆者はすぐに知ることになる。
その数日後、別の女性起業家のB子さん(40代)の話を聞いたが、こちらは最初から最後まで、思い詰めた雰囲気が漂っていた。
彼女が乳がん宣告を受けたのは、37歳の時だ。
「30歳で会社を辞めて、独立して、馬車馬のように働いてきた。会社が落ち着いたころ、ちょうど同じ年齢のパートナーと婚約もして、あとは結婚して子どもをつくるだけだったんです。まさかそのタイミングで自分が乳がんに罹るなんて、夢にも思っていなかった」
会社は共同経営者に任せ、闘病生活に入った。友人には支えてもらったが、婚約は破談となった。
「彼が子どもをほしがっているのを知っていたからです。彼にとっては、『結婚=子どもを持つこと』なのに、私は完治するかどうかもわからない病気に罹り、子作りなんて無理だった。お互い、恨んだり嫌いになったりする前に、別れました」
と、言った。闘病生活は約4年にわたり、今も独身のままだ。もちろん、子どもはいない。
「今って、卵子をとっておくことができるじゃないですか。もっと元気で若い時にそういう選択肢を知っていれば、彼と別れなくてすんだのかなって……。でも、乳がんから生還できるかわからなかったから、やっぱり無理だったのかな」 (2020年10月22日「WiLL online」掲載)










